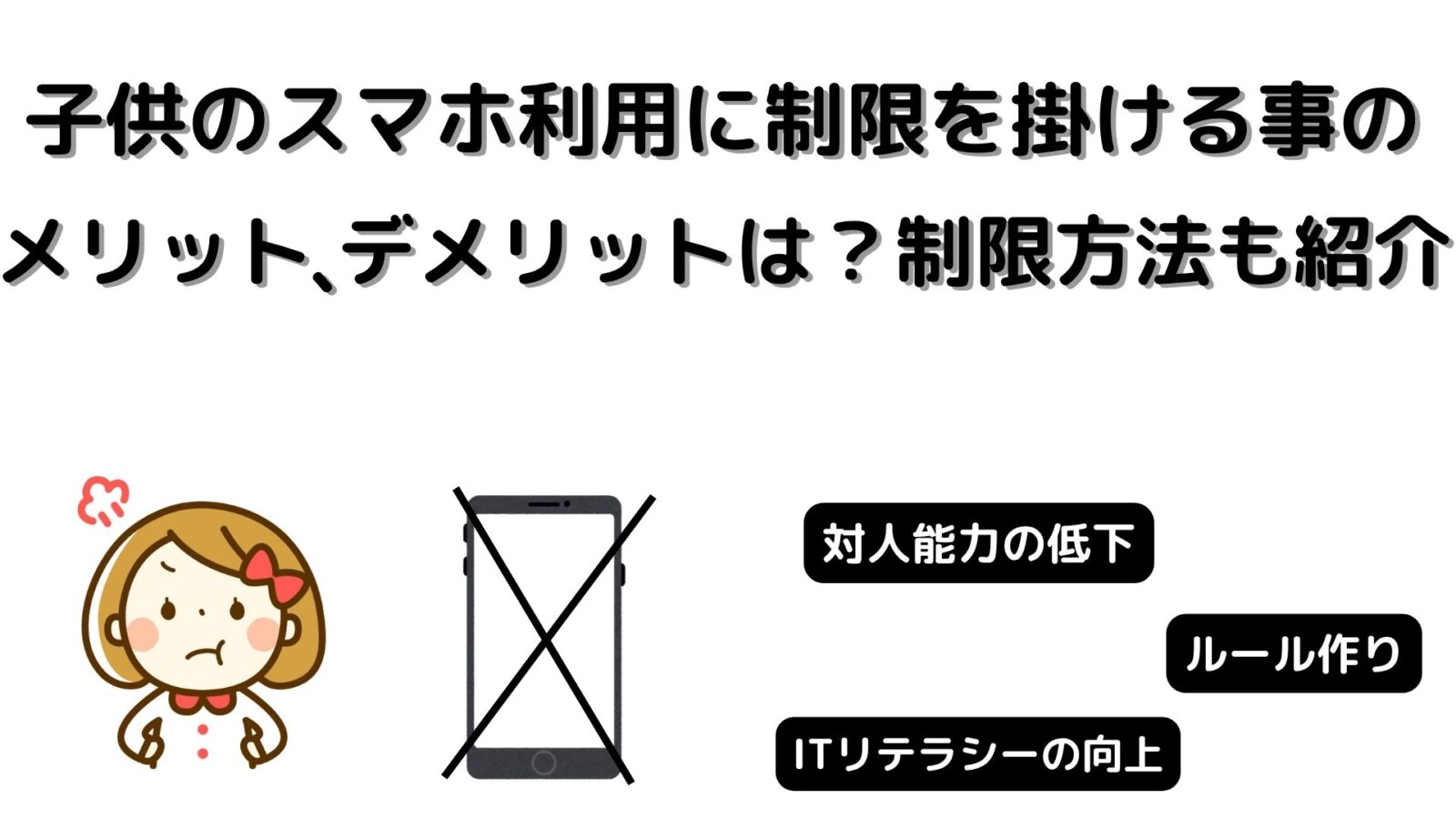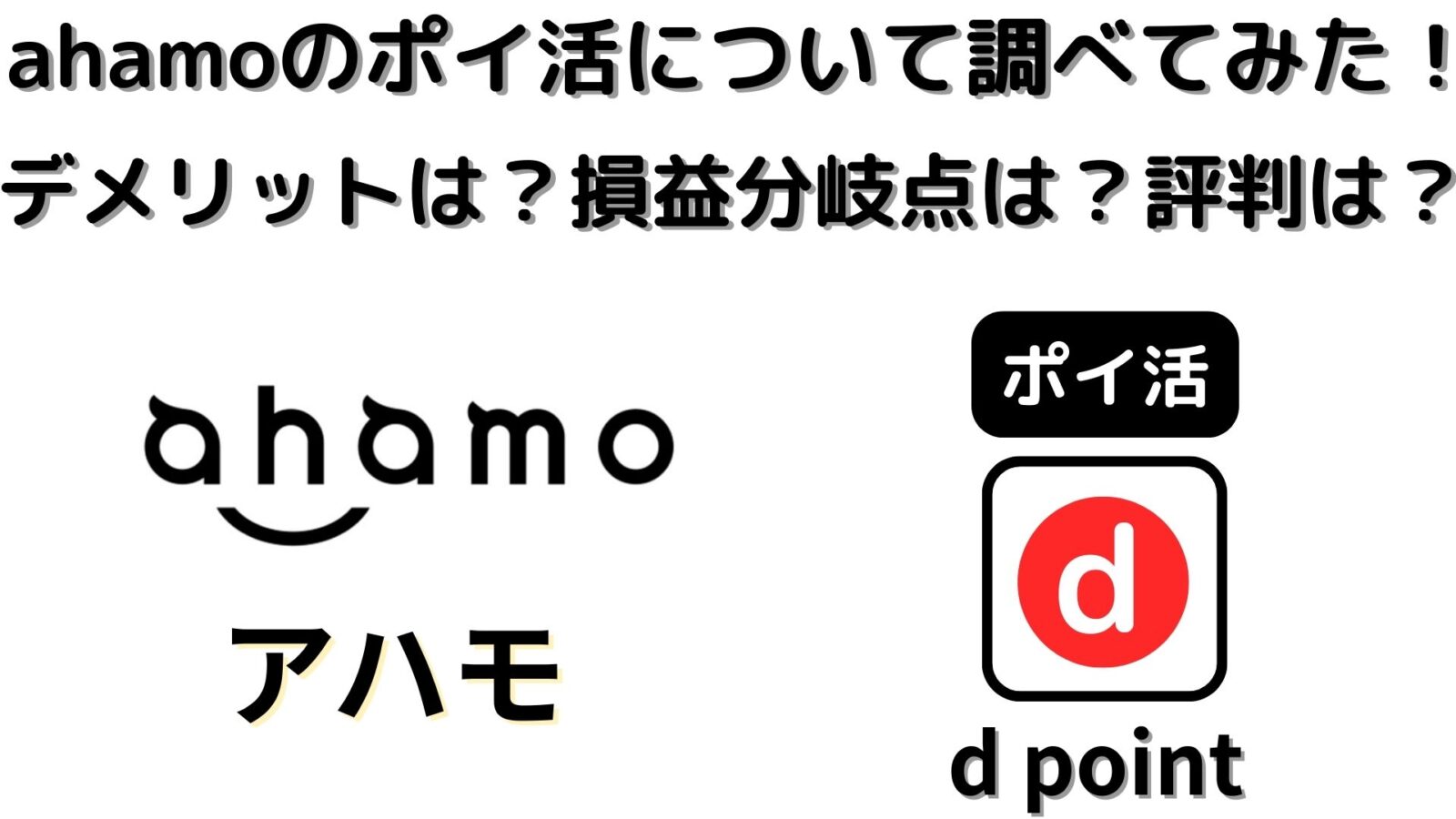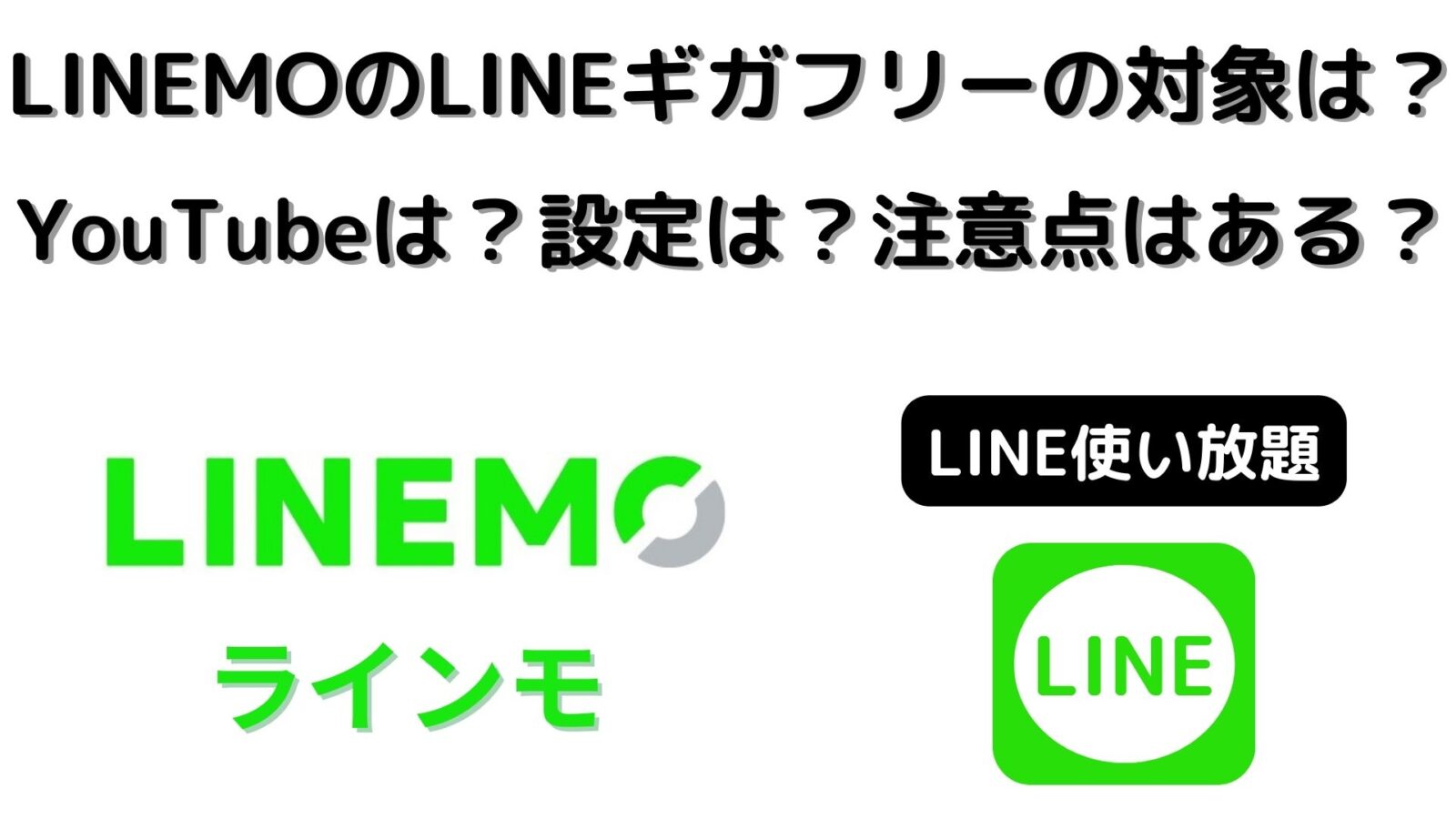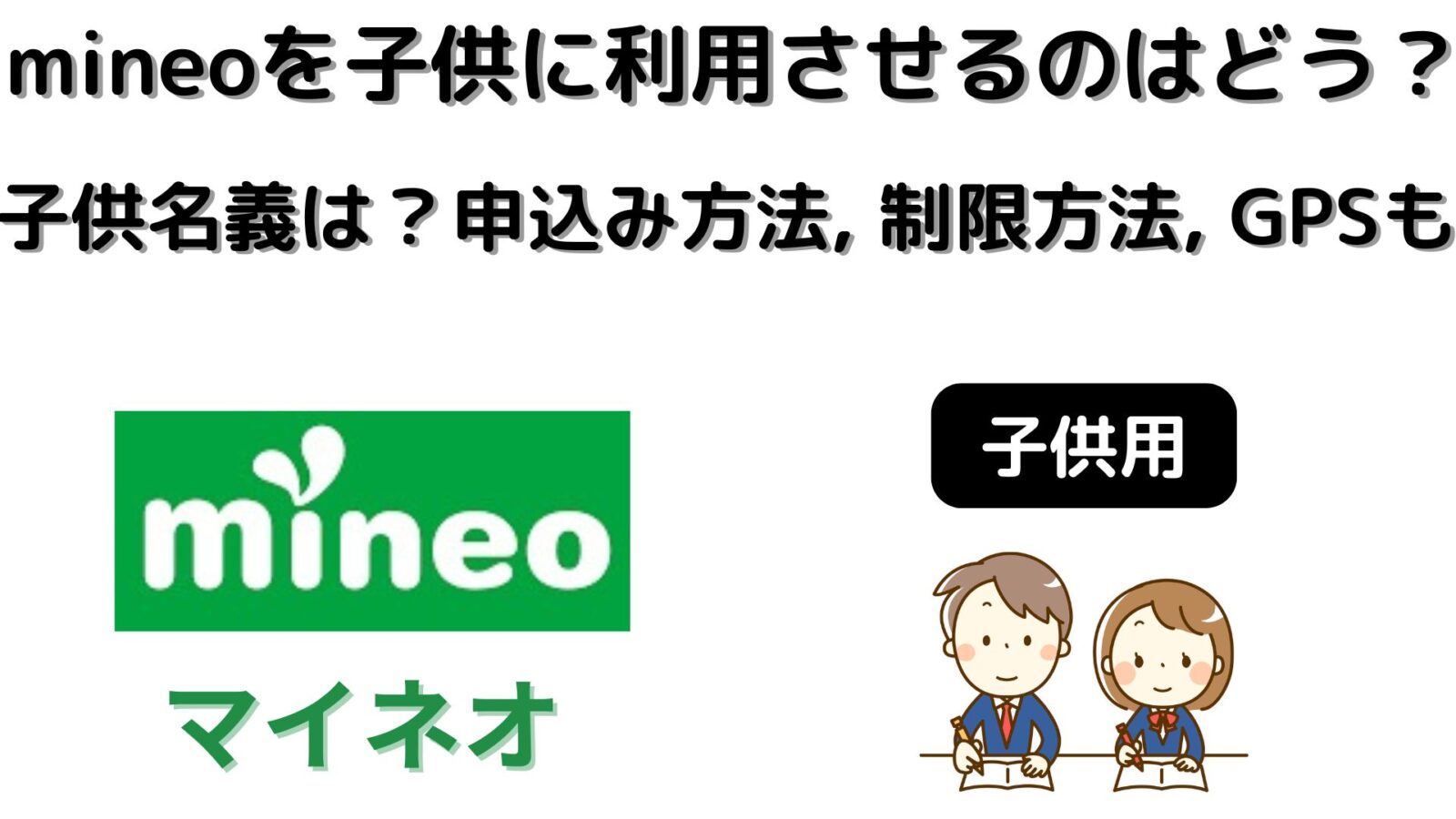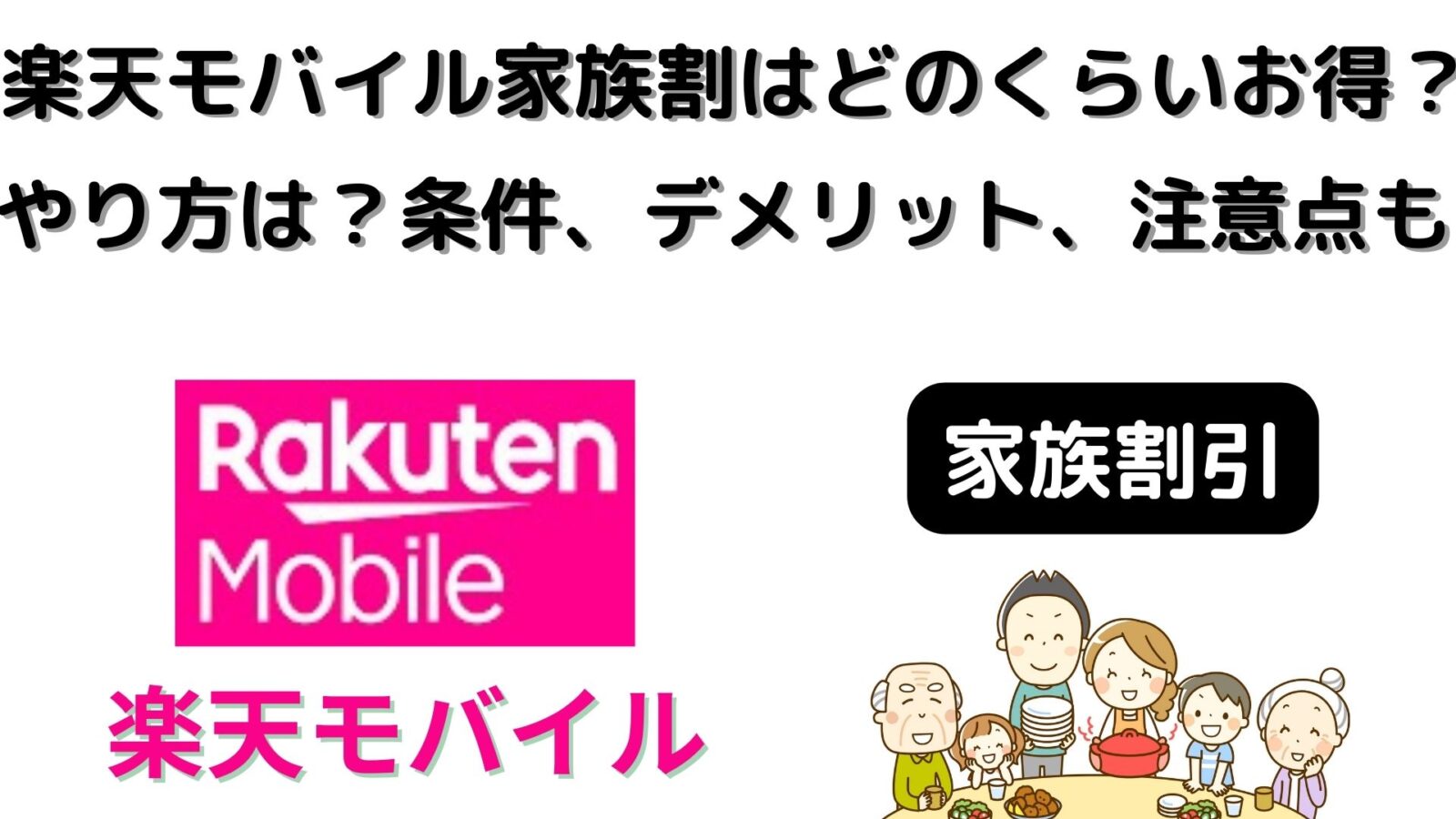子供のスマホを制限する事のメリット
子供にスマホを持たせる際には、利用時間の制限、サイト閲覧のフィルター、アプリのブロック、支払い制限などを掛ける事が可能となっています。
この章では子供のスマホに上記のような制限をする事で一体どのようなメリットがあるのかについて、詳しくご紹介させて頂きます。
健康的な生活が送れる
スマートフォンの使い過ぎは、健康に様々な悪影響を与える可能性がございます。
たとえば、猫背、凝り、首痛、目の疲れ、不眠症などがあります。
また、身体的な影響以外にも依存症、不安障害、うつ病など精神的な問題も引き起こすリスクもあります。
そこで、スマホの使用を制限する事によって、外で身体を動かす時間や家族と外出する時間を確保する事ができます。
それによって、体力がついたり、生活習慣病を予防できたり、筋力の増強など健康にとって良い効果が生まれやすくなります。
また、屋内にいる時間を減らし、外に出て日光を浴びる事は睡眠の質の向上やメンタルヘルスを良好に保つ事に繋がったり、歩く機会が増える事で健やかな毎日を送りやすくなります。
リスクを避けられる
スマートフォンを利用する事で、日常生活を便利に送れると同時に様々なトラブルに遭うリスクも潜んでいます。
具体的には、ウイルスへの感染、個人情報の漏洩、高額な料金請求、詐欺被害などが挙げられます。
スマートフォンを制限する事は、普通に日常生活を送る上では起こり得ない様々なトラブルを回避する事にも繋がります。
ネットを利用する際には事前にどのようなリスクがあるのかを理解した上で、万が一を想定して対策を講じておくことが極めて重要となります。
リスクの主な例
- ウイルス感染
開発元が不明なアプリの利用などにより端末がウイルスに感染すると、個人情報が漏れたり、端末を不正に利用されてしまう可能性がございます。
- 個人情報漏洩
偽サイトにログインをしてしまったり、メールなどからのフィッシング詐欺に引っ掛かってしまうと、IDやパスワードが盗み取られてしまう可能性がございます。
- 人間関係トラブル
実際に現実で言葉を交わすのとは違い、ネット上での文字だけでのやり取りでは双方で思い込みや勘違いなどが発生しやすくなります。
そのため、ネットでのコミュニケーションに依存し過ぎると、人間関係に亀裂が生じやすくなります。
- 嫌がらせ被害
SNSで投稿した出来事や画像などから、住んでいる地域などが特定される可能性がございます。
また、誹謗中傷や悪口を含んだコメントをされて、精神的なショックを受けるリスクもあります。
依存を防げる
スマートフォンに依存するようになると、日常生活に様々な支障が出てくるようになります。
スマホの利用時間を自分の力では調整する事ができなくなったり、数時間使用できない状況になると不安感を覚えたり、利用を控えようとしても我慢する事ができなくなります。
このようなスマホ依存症に陥ってしまうと本来、自分がやらなくてはいけない事に集中する事ができず、なかなか作業が捗らなくなってしまいます。
日常生活においては主に睡眠時間、食事時間、勉強時間などに影響が出やすくなります。
依存症になってしまうと・・・
- 長時間利用
家にいる時間のほとんどをスマホ利用で過ごすようになります。
食事、睡眠、勉強、入浴等の時間を削ってでも、利用する時間を確保しようとします。
- 歯止めが効かなくなる
長時間使用している事を自覚していても、本人の力では使用を中断する事ができなくなります。
また、熱中するがあまり、時間の経過を忘れてしまう事もあります。
- メンタルの悪化
スマホが使用できない状況になると落ち着かなくなります。
また、ストレスからイライラしたり、他人にも強く当たるようになります。
- 私生活への影響
スマートフォンにしか気が回らなくなり、学業のパフォーマンスが著しく低下したり、外での活動を控えるようになったりします。
対人能力の向上
ネットの利用時間の増加は、リアルでコミュニケーションをとる時間の減少に繋がり、対人能力の低下を引き起こす恐れがあります。
また、スマホの時間が増える事によって、対面で話す機会が失われると、社会性の発達に影響を及ぼす可能性もございます。
また、学校生活において何か困り事や不安な事があった際に対人能力を築けないでいると、自分から相談する事を躊躇ってしまったり、我慢してしまうといった事にも繋がります。
対人能力が低下してしまうと・・・
- 読み取る力の低下
画面を通したコミュニケーションが大半になると、対面で話す機会が減り、人間関係を構築する力や相手の表情や声量から意図を読み取る力が低下します。
- 家族仲への影響
家族とのコミュニケーションも円滑に取る事ができなくなり、家族仲に悪い影響を及ぼす可能性があります。
また、相談を控えたりするようになります。
- 孤立感が強まる
対人能力が低いと友人とのコミュニケーションを避けるようになり、一人で過ごす時間が増える為、孤立感が強まる可能性があります。
- 自主性の低下
グループ学習などで積極的に自分から意見を発言したり、対話を行なおうとしなくなるため、自主性の低下に繋がる恐れもあります。
子供のスマホを制限する事のデメリット
上記の章にて、子供のスマホを制限する事のメリットを挙げさせて頂きましたが、一概に厳しく制限すれば良いというわけでもありません。
制限する事によって、様々なデメリットも同時に生じる事となります。
具体的には、情報収集手段の減少、クラスメイトや同級生とのコミュニケーション機会の制限、親子関係への影響、ITリテラシーの低下などが挙げられます。
また、過度な制限によって、子供の反発を招く恐れもございます。
情報収集機会の減少
スマートフォンを持つとSNS、検索エンジン、多数のアプリ、動画コンテンツなど様々な手段にて、自分の知りたい情報を瞬時に調べる事が可能となります。
スマホはいつでもどこでもネットを利用する事ができるため、疑問に感じた事をすぐに調べたり、困った時に解決策を見出したり、非常に効率的に情報収集を行う事ができます。
また、時刻表アプリや天気予報アプリなどで日常生活に役立てる事もできますし、翻訳アプリや辞書アプリなどを用いれば学習に役立てる事も可能です。
スマホに制限を掛ける事でこれらの便利機能が使えなくなる場合があります。
主な情報収集ツール
- SNSのタイムライン
よりリアルタイムでの情報を収集したい時に役立ちます。
交通情報や天気、災害の情報など様々な面において情報を集める事ができます。
- 検索エンジン
調べたいワードや事象を入力するだけで、必要な情報を多くのサイトから幅広く集める事ができます。
また、調べたい動植物などを画像を用いて検索する事もできます。
- 動画コンテンツ
様々な教科の学習動画が無料で公開されており、予習や復習、受験対策などに役立てる事ができます。
また、社会情勢について議論したり、解説している動画などもございます。
- AIアプリ
調べたい事について入力をすると、会話形式にて疑問を解決に導いてくれます。
AIアプリは年々、進化を遂げており、従来では難しかった高度な処理や高度なタスクを実行できるものも出てきています。
- 天気、交通、ニュースアプリ
現在の天気や交通情報、最近起こったニュースなど専用のアプリをインストールする事でその情報に特化した情報を効率良く収集する事が可能となります。
友達とのコミュニケーション機会の減少
子供のSNSの利用を制限すると、友達とのコミュニケーション手段の減少、学校生活についての連絡手段の減少、勉強についての相談や情報共有、習い事や部活動などのグループに参加できない、といった友人との関係構築や維持に影響を及ぼす可能性がございます。
SNSの利用を制限する事への影響
- 関係構築への支障
SNSは友達と他愛もないやり取りであったり、日常的な連絡、意見交換、共通の趣味などを共有する場として活用されています。
それらが利用できなくなる事で友達との友好関係を築きにくくなる場合があります。
- 疎外感
部活動や習い事、共通の趣味を持った友達とでSNSにてグループが作成されていた場合、自分だけが輪の中に入れない事で疎外感や孤立感を感じてしまう場合があります。
また、連絡事項などがあった際に情報を受け取れない可能性もございます。
- 学習へのモチベーション
SNSはテスト前の進捗共有、切磋琢磨するためのツール、課題の確認など学習においても有効活用される場合があります。
モチベーションの維持や友達と競い合って相乗効果を生むといった事ができなくなります。
親子仲への影響
スマホを制限するとそれによって親子仲へ影響を及ぼす可能性がございます。
とくに一方的に制限したり、子供の意見を聞かずに親が独断でルールを作ってしまうと、より子供からの反発を招く事に繋がるため注意が必要です。
子供が反発する理由としては、スマホが日常の娯楽の一つとして利用されている事や友達とのコミュニケーションに必要不可欠なツールになってきている事、自分の意志に反した制限が課される事などが挙げられます。
そのため、あまりにも制限する度合いが強すぎると、逆にスマホへの執着心を強める結果となり、さらに親子仲が悪くなるという悪循環に陥る場合があります。
制限での親子仲への影響
- ストレス増加
スマートフォンが日常的な楽しみやストレス発散方法として根付いてしまっている場合、制限をするとストレスが増加して常にイライラするようになります。
- 執着が強まる
制限が厳しすぎたり、監視をし過ぎると却ってスマホへの執着心を強め、さらに反発を強める事にも繋がります。
- 信頼関係の欠如
親が一方的に制限を行なったり、話し合いが不十分で子供の理解を得られないまま、いきなり制限を掛ける事によって、子供の親に対する信頼を損なう事にもなります。
ITリテラシーの低下
ITリテラシーとは、情報技術の知識やスキルを身に付け、それらを適切に活用できる能力の事を指します。
具体的には、コンピューターやインターネットを使っての情報収集や分析、セキュリティへの意識、最新のIT技術を活用する能力などが含まれています。
スマホを制限する事によって、これらの能力が身に付くチャンスを逃す事にも繋がります。
とくに現代の社会はあらゆるサービスのIT化が進んでおり、ITリテラシーは必須のスキルとなってきていると言っても過言ではありません。
ITスキルを身に付けるには小さいうちから機械やネットに触れ、情報収集力・判断力・トラブルシューティング力を培っておく事は大切です。
また、最近ではスマホやAIの普及によって、ITリテラシーはこれからますます重要視されていくとも言われています。
スマホ利用で身に付くITリテラシー
- 情報セキュリティ
パスワードを管理する能力、怪しいメールや偽物サイトを避けるなど個人情報の漏洩やID、パスワードの流出を防ぐための対応力などが身に付きます。
個人情報の取り扱いやプライバシーに配慮する力なども培えます。
- 情報判断力
インターネット上のありとあらゆる情報において、信頼性や正誤を判断する能力が身に付きます。。
フェイクニュースや印象操作を目的とした情報ではないかを識別する力も培えます。
- トラブル対応力
スマホの操作方法やネット接続のトラブル時など、様々なトラブルに対応する能力が身に付きます。
アプリの設定方法や正常動作しない時など不測の事態に対しても慌てる事なく対処できるようになります。
- ネット上でのモラル
ネット上での適切なマナーやモラルを学ぶ事ができます。
また、誹謗中傷や暴言、言い争いなどから自分を守る方法や対処する術などを身に付ける事ができます。
子供のスマホの適切な制限の仕方について
先述にて子供のスマホを制限する事のメリット、デメリットについてお伝えさせて頂きましたが、こちらの章では子供のスマホの適切な制限方法についてお伝えさせて頂こうと思います。
これから子供にスマホを購入しようと思っている方、これから子供のスマホを制限しようと思っている方、子供のスマホを制限しようか迷っている方などはぜひ、参考にして下さい。
ルールを作る
子供のスマホのルールを作る際は年齢や親の教育方針に合わせて、しっかりと子供と話し合いを行ないながら、お互いに納得する形で決めていく事が望ましいです。
主に「利用できる時間」「利用できる場所」「利用用途」「利用できるアプリ」など、より具体的に細かくルールの内容を決め、定期的に親子でルールを見直していく事も大切です。
また、ルールを破った場合にはどのような罰を受けるかも予め決めておくことで、後々、言い争いやトラブルになるのを防ぐ事ができます。
ルールを作る際のポイント
- 子供の主張も聞く
子供の年齢やスマホを使う目的などを考慮しつつ、親だけではなく子供の主張も聞きながら、お互いに納得のできる形でルールを決めていくようにしましょう。
- 理解をさせる
作ったルールを一方的に子供に押し付けるのではなく、なぜスマホの制限を掛ける事が必要なのかを十分に説明し、理解を促していく事も大切になります。
- 親も一緒に協力する
子供だけスマホの利用を控えさせるのではなく、親も一緒になってスマホの利用を控える努力をしていきましょう。
親が長時間、スマホを利用していると子供は差別的な感情を抱きやすくなります。
制限の強度を年齢に合わせる
スマホの制限を厳しくしすぎると、子供になかなか理解してもらえず、協力を得られにくくなってしまいます。
重要なのは子供の年齢や成長段階に合わせて、制限の強度を調整していく事になります。
そこでオススメとなるのがキャリアから提供されているフィルタリングサービスです。
フィルタリングサービスにはカスタマイズできる機能が備わっており、親が子供のスマホ利用を細かく管理できるようになっています。
フィルタリングサービスを活用する事によって、最適な制限を掛ける事が可能です。
年齢や学年などに合わせて、ウェブサイトやアプリの利用可否の設定をカスタマイズしたり、利用時間や利用内容の確認ができます。
おすすめのフィルタリングサービス!
Y!mobile
- お子さまの年齢に合わせて制限可能!
- 小学生モード、中学生モード、高校生モードを搭載!
- 68種類ものカテゴリから「見せる」「見せない」を細かく設定できる!
\ Y!mobileの公式ページへジャンプ! /
楽天モバイル
- 年齢にあったフィルタリングを簡単設定!
- カテゴリを選択するだけで細かな設定が可能!
- 必要なサイトだけ見せる事もできます!
\ 楽天モバイルの公式ページへジャンプ! /
LINEMO
- お子様の学齢・知識・判断力に合わせて強度が選べる!
- 要望に応じてサイト閲覧の許可ができる!
- 67種類のカテゴリから、見せて良いカテゴリと見せたくないカテゴリを選択可!
※Androidの方はファミリーリンクをお使い下さい。
\ LINEMOの公式ページへジャンプ! /
ahamo
- アクセス制限されるサイトを選べる!
- アクセス制限されるカテゴリを選べる!
- 親が自由にカスタマイズする事ができます!
\ ahamoの公式ページへジャンプ! /
mineo
- 年齢に合った設定ができる!
- ご家庭の方針に合わせて、範囲を自由に設定可能!
- Webページ・アプリのカテゴリ別設定も簡単!
\ mineoの公式ページへジャンプ! /
まとめ
子供のスマホを制限する事のメリットとしては、
- 健康的な生活を送れるようになる
- スマホ起因による様々なリスクを避ける事ができる
- スマホ依存症に陥るのを防ぐ事ができる
- 対面で会う機会が増え、対人能力を育む事ができる
などの様々な恩恵がございます。
その一方で、スマホの制限をする事によって、
メリットだけではなく、デメリットも生じやすくなります。
スマホ制限による主なデメリットとしては、
- 情報収集する機会を損失する事に繋がる
- 学校時間外での友達とのコミュニケーション機会の減少
- 親子関係の悪化に繋がる恐れがある
- ITリテラシーを培う事が難しくなる
といった事などが挙げられます。
子供のスマホの適切な制限方法については、
- 親子でよく話し合って、ルールを決める
- 制限の強度を年齢に見合ったものにする
以上の2点が重要となります。
制限の強度を年齢に合ったものにするには、
キャリアから提供されているフィルタリングサービスを利用するのが、
一番簡単、かつ適切に設定できる事ができるのでオススメです!
皆さんもこの機会にぜひ、当記事を参考にしながら、
子供のスマホを適切な範囲にて、制限されてみてはいかがでしょうか?