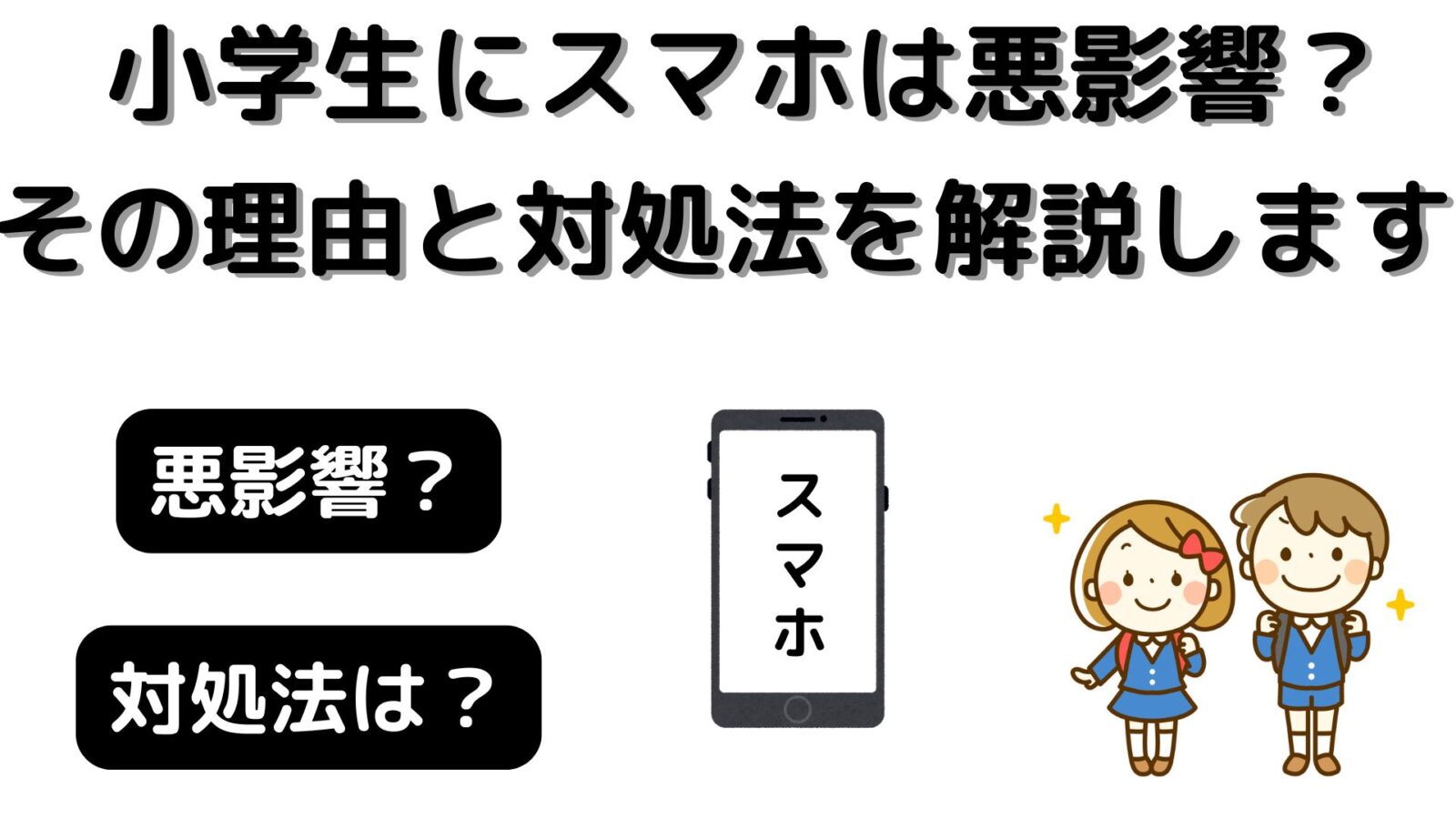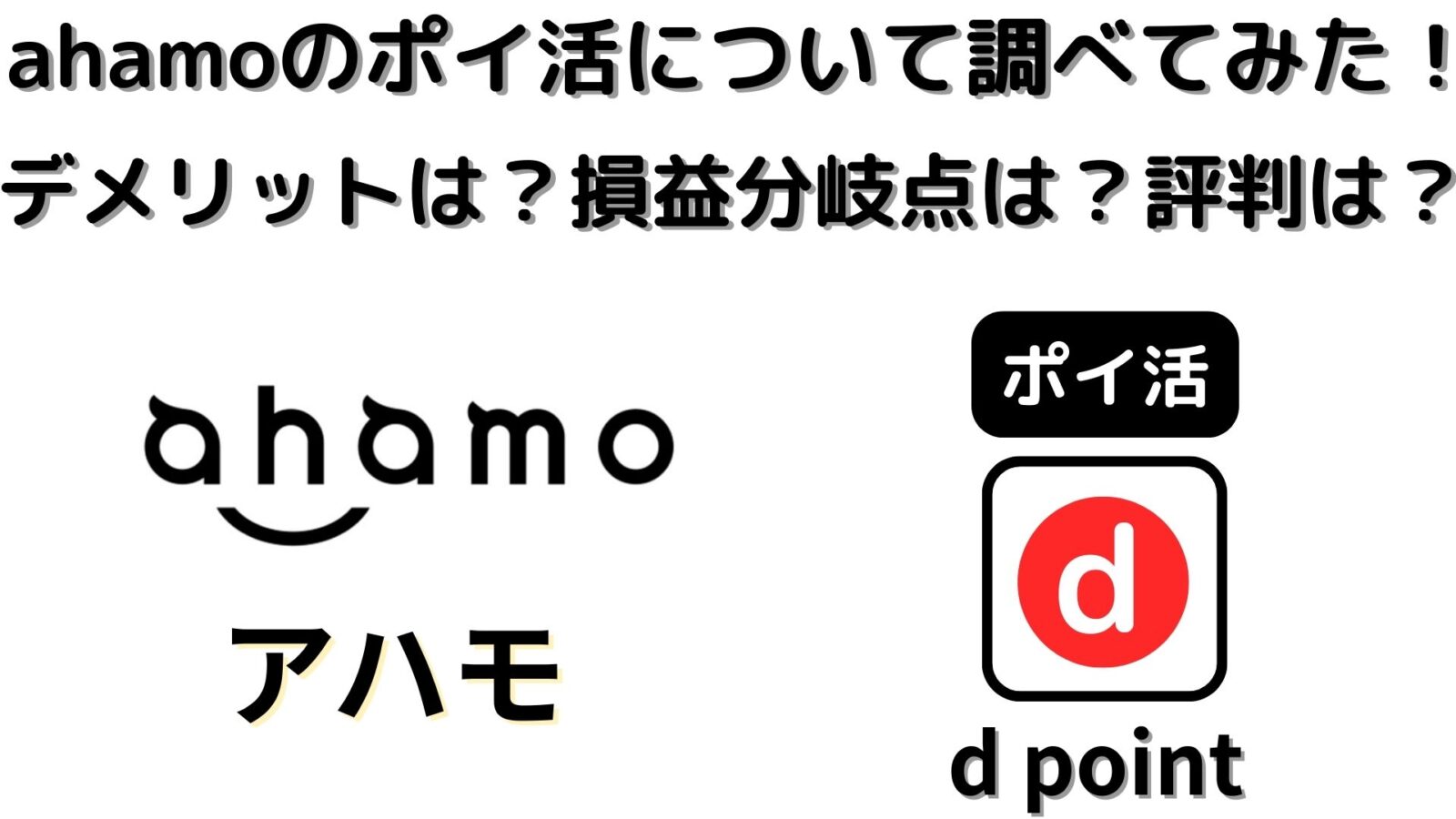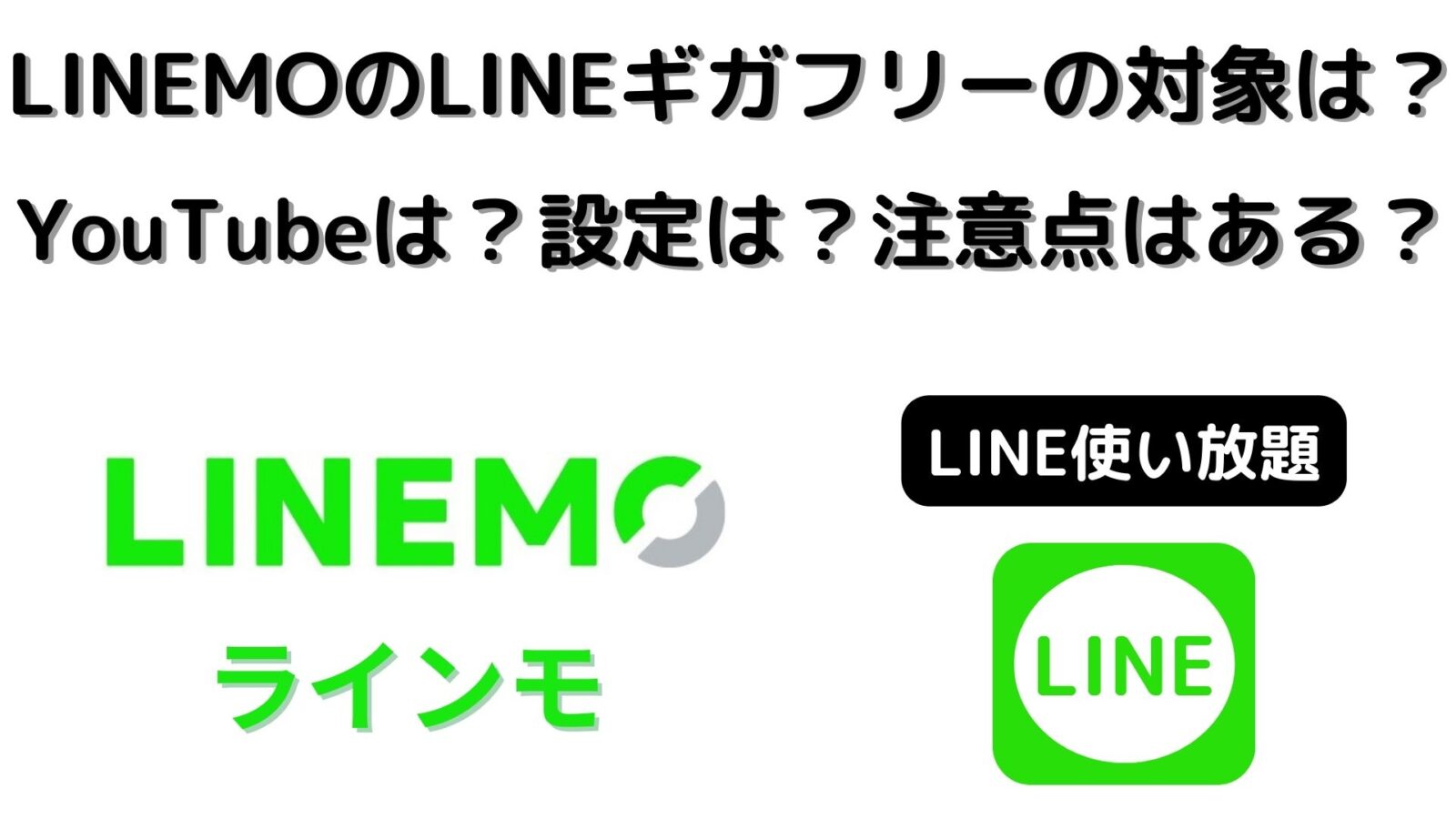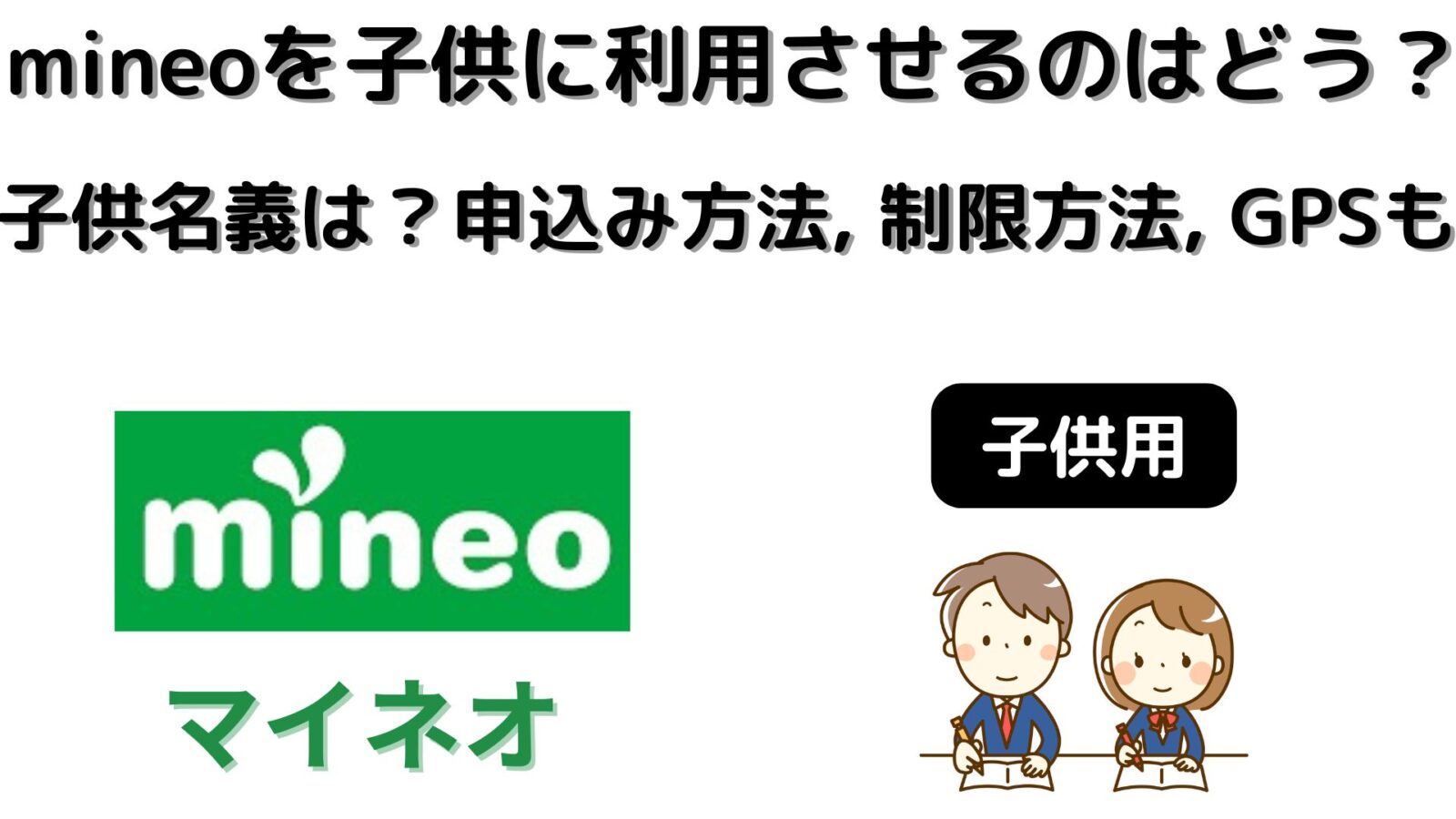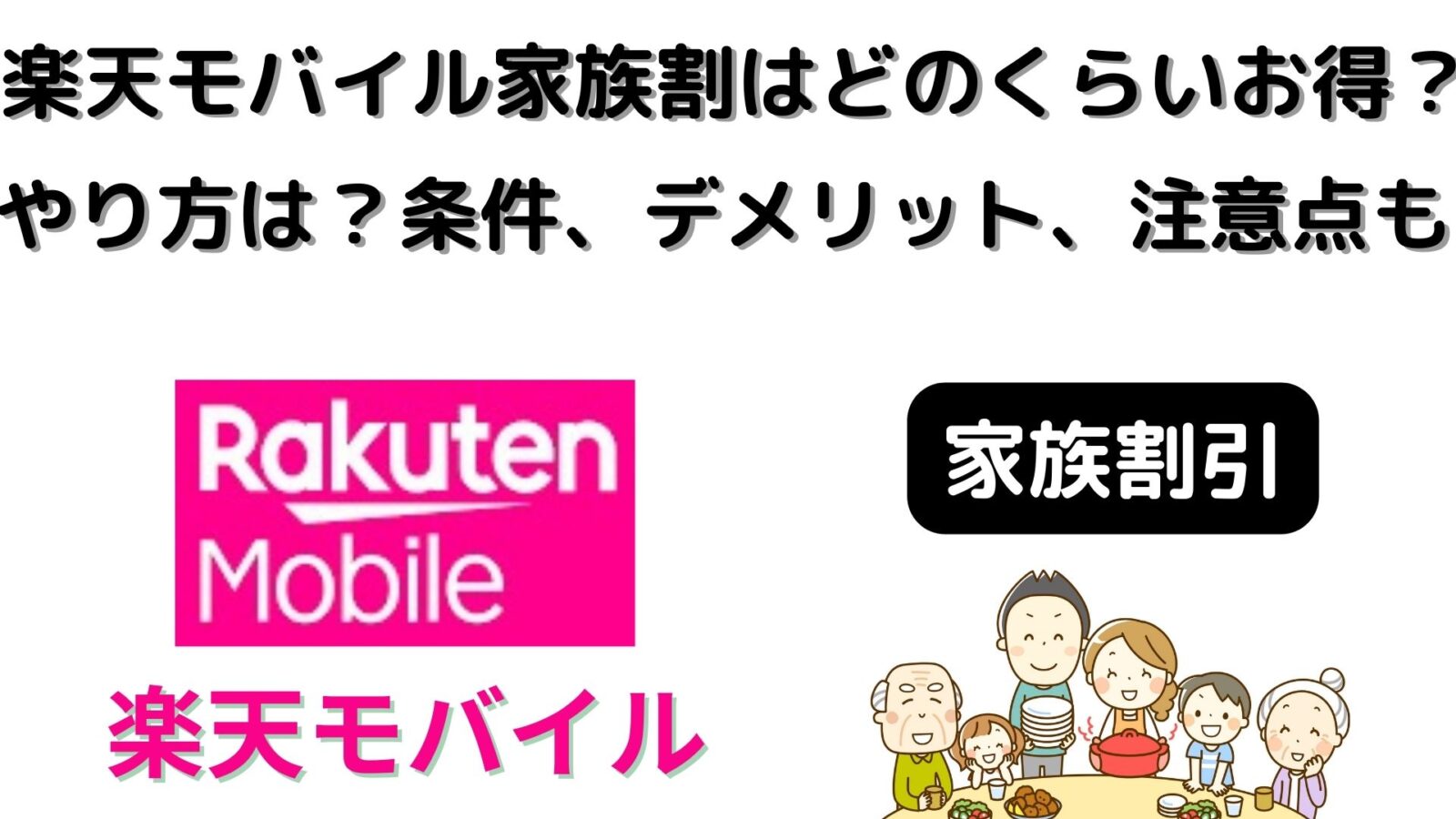スマホが小学生に与える悪影響には何があるのか?
小学生がスマホを持つ事によって「視力への影響」「睡眠への影響」「学力への影響」「長時間利用」「トラブルのリスク」など、様々な悪影響が想定されます。
スマホの長時間利用によって、不適切なコンテンツを見る機会が多くなると、子供の成長に好ましくない影響を与える可能性がございます。
この章では、スマホが小学生の子供にどのような影響を及ぼす可能性があるのかについて紹介させて頂きます。
視力への影響
スマホの長時間利用は「眼精疲労」「ドライアイ」「視力低下」「近視や斜視」となる可能性があります。
スマホから発するブルーライトの影響やディスプレイを長時間見続ける事で目の周りの筋肉が緊張する事がこれらの症状を引き起こす要因となります。
そのため、スマホの長時間の利用はできる限り、避ける必要があります。
スマホの目に与える影響
- ドライアイ
スマホを長時間見続けると、瞬きの回数が減り、目が乾燥しやすくなります。
乾燥によって、目の違和感、不快感、目が疲れやすくなる場合もございます。
- 視力低下
近距離でディスプレイを見続けると、筋肉が緊張しやすくなります。
特に子供はまだ目が成長途上であるため、影響を受けやすく、やり過ぎる事で視力の低下にもつながります。
- 眼精疲労
スマホを見続けると目が疲れやすくなり、かすれや筋肉の痛み、チカチカなどの症状が現れる場合がございます。
また、それと同時に頭痛や肩こりなど他の身体症状を併発する恐れもあります。
- ブルーライト
ディスプレイから発するブルーライトはチラつき、まぶしさによって、通常よりも目への疲労がたまりやすいです。
また長時間、強い光に当たり続ける事によって深い睡眠が取りづらくなる事も考えられます。
睡眠への影響
スマホを使い過ぎてしまうと、睡眠不足を招く恐れがあります。
とくに入眠するギリギリまでスマホを利用していると、スマホから発するブルーライトの影響によって、睡眠ホルモンの一種であるメラトニンの分泌を抑えてしまい、寝つきを悪くしたり、睡眠の質を大幅に低下させてしまう可能性があります。
スマホの睡眠への影響
- 強い光
スマホの画面から出る強い光によって、脳が昼間だと勘違いし、覚醒させてしまいます。
それと同時に睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を抑制するため、寝る前にスマホを操作していると入眠しにくくなります。
- 質の低下
寝る直前までスマホを操作する事は、脳が興奮状態になりやすく、寝つきが悪くなります。
また、レム睡眠とノンレム睡眠のバランスが崩れ、ノンレム睡眠(深い睡眠)の時間の減少にも繋がり、起きた時にスッキリと起きられなくなります。
- 脳への影響
慢性的な睡眠不足は集中力を低下させたり、記憶力を低下させる事にも繋がります。
また、日中の活動時間に眠気に襲われたり、免疫力が低下しやすくなったりと、私生活にも影響が出る場合がございます。
- 睡眠環境
十分な睡眠を確保するにはより良い睡眠環境を作る事も重要となります。
寝室の光を落としたり、入眠前にスマホをいじらないように、寝具にスマホを置かないようにするのも大切です。
寝る1~2時間前はスマホを触らないようにするなどルールを決めるのも良いでしょう。
勉学への影響
スマホの使い過ぎは勉強に悪影響を与える可能性がございます。
特にスマホの利用時間と勉強成績には、強い関係がある事が研究でも分かってきています。
スマホを長時間利用していると、集中力の低下や記憶力の低下等を引き起こし、また睡眠時間も短くなりやすいため、学習効果を低下させてしまいます。
スマホの勉学への影響
- 集中力や注意力
SNSでの更新チェックや自分の投稿への反応チェックなどの誘惑により、勉強に集中する事が難しくなります。
また、スマートフォン端末の通知機能も勉強を妨げる一因となります。
- 脳疲労
常にスマホから多くの情報を取り入れていると脳が疲れ、脳疲労を引き起こす可能性があります。
休憩を取り入れずに長時間スマホを利用するケースが多い方はとくに注意が必要です。
- 定着力の低下
スマホの利用し過ぎにより、睡眠の質が低下してしまうと、勉強をしても内容が定着しにくくなります。
睡眠前にスマホを利用しすぎない事が重要になります。
- 発達への影響
スマホですぐに色々な問題を解決してしまうと、自分で深く考える力や問題を解決する力が育ちにくくなる可能性があります。
まずは自分で考える事を優先し、それでも分からない場合は利用するといったクセをつける事も大切です。
運動への影響
スマートフォンの利用は運動不足や体力の低下、姿勢の悪化など、様々な身体への影響を招く恐れがございます。
特にスマホの利用時間が長くなればなるほど、屋内で座っている時間も増えますので、筋力が減少したり、血流が滞りやすくなります。
また、運動する際に歩きながらスマホを利用すると、転倒のリスクや身体の凝り、腰痛や猫背の要因にもなります。
スマホの運動への影響
- 運動不足
利用時間が多くなればなるほど、屋外で運動する時間を減らす事に繋がり、ひいては慢性的な運動不足へと発展しやすくなります。
そのため、運動する習慣を定期的に作る事が重要になります。
- 筋力低下
椅子に座ったり、寝転んでいる時間が長くなると、筋力が低下する事にも繋がります。
また、筋力が低下すると身体能力も落ちやすくなります。
- 姿勢の悪化
スマホを利用すると、どうしても同じ姿勢になりがちです。
それによって、猫背や肩こり、首こりや腰痛などを招く恐れがあります。
- 反射神経の低下
過度なスマホ利用は、認知機能や反射神経に影響を与え、反応が鈍くなる可能性がございます。
また、筋力が低下するとちょっとした物に躓きやすくなり、ケガのリスクも増加します。
小学生がスマホを使う事が悪影響にならないようにするためには?
小学生がスマホを持つ際に気を付ける点としては「利用時間」「利用場所」「使用するアプリ」「課金」「個人情報」「トラブル時の対応」などがございます。
これらの様々な点において、事前にしっかりと話し合ってから利用する事が大切となります。
また、フィルタリングサービスなどで子供がスマホをどように利用しているのか、保護者が定期的に利用状況を確認するのも有効な手段となります。
この章では小学生のスマホ所持が悪影響とならないようにする為の方法について、ご紹介させて頂きます。
親が管理する
スマホを親が管理する際には子供としっかりと話し合い、できる限り両者が納得できる管理方法にする事が重要となります。
「時間」「場所」「使えるアプリ」「課金額の上限」などを予め、しっかりと決めて置き、好ましくない使い方をしている場合には、保護者が随時注意するように心がけましょう。
また、ルールなどを作るのも効果的です。
親子間で決めたルール厳守を徹底させ、守れなかった場合にはスマホ利用を数日間禁止にするなど、事前にペナルティなども決めておく事で言い争いなどを未然に防ぐ事ができます。
親が注意する点
- 時間
1日にスマホをどのくらい利用しているのか注意深く見るようにしましょう。
やり過ぎている場合には注意をして、休憩を促す事も大切となります。
- 場所
勉強中や食事中、就寝前など使用してはいけない場所を予め、決めておくようにしましょう。
指定した場所にスマホを持ち込んでいないか、常日頃からチェックする事が重要になります。
- アプリ
使って良いアプリを予め、決めておくと管理がしやすくなります。
また、課金ができるようなアプリは親の許可を得るようにしたり、上限額を設ける事も大切です。
- SNS
知っている友達とのやり取りのみを許可したり、不特定多数の人に公開しないなど、利用できる範囲を決めておきましょう。
誹謗中傷や悪口などを書かないようにするなど、子供へSNSを利用する際の注意点などを日頃から指導しておく事も有効です。
- ながらスマホ
歩き中のスマホや食事中にスマホを利用していないかを注意して見るようにしましょう。
作業中はその作業に集中し、スマホはいじらないようにするなど、親がしっかりと子供の日頃の行動を管理するようにしましょう。
キャリアのフィルタリングを使用(おすすめ)
キャリアから提供されているフィルタリングサービスとは、青少年が教育に適切ではない情報にアクセスしないように未然に防ぐサービスとなります。
インターネット上には様々な有害サイトやアプリなどが存在しており、お子さんの年齢や学年などにそぐわないアプリやサイトの利用を制限する事によって、安全なスマホの利用環境を作る事ができます。
フィルタリングの強度やフィルタリングをかけるカテゴリーなどは保護者が自由に決める事ができます。
お子様の成長段階に合わせて、その都度調整していくようにしましょう。
フィルタリングサービスでできる事
- サイト制限
成人向けのサイトや暴力的なサイトなど、教育上ふさわしくないサイトへの閲覧を制限できます。
- アプリ制限
推奨年齢が指定されているアプリや中毒性のあるアプリなどの利用を制限する事ができます。
- 時間制限
アプリを利用できる時間、サイトを閲覧できる時間などを細かに設定し、スマホ依存症になるのを未然に防ぐ事ができます。
- 課金制限
インストールする際に料金が発生するアプリの利用を禁止します。
また、アプリ内での課金を制限できます。
- 位置情報
位置情報を把握し、子供が現在どこにいるのかを把握する事ができます。
また、位置情報の利用を制限する事で個人情報を守ります。
- 検索制限
不適切なワードで検索できないように制限をする事が可能です。
検索結果から不適切なサイトを除外する事もできます。
▼フィルタリングサービスを提供しているキャリアはコチラからどうぞ!
端末の制限機能を使う
スマホ端末での制限は、主に子供がスマホを安全に利用できるように「利用時間」「コンテンツ」「アプリ」などを制限できる機能となります。
Android端末とiPhone端末ではそれぞれ設定方法が異なります。
また、GoogleアカウントやApple IDなどのアカウントを使って利用できる機能に制限を掛ける事も可能です。
Androidの制限方法
●ファミリーリンク
Googleアカウントを使って、子供の端末を管理する事ができます。
管理できる内容は以下になります。
- 時間制限
- アプリ制限
- コンテンツ制限
- 位置情報の確認
●デジタルウェルビーイング
Android端末に備わっている機能の一つで、アプリごとの利用時間を確認したり、アプリの利用の制限を設定する事ができます。
管理できる内容は以下になります。
- 利用時間確認
- アプリ制限
- 通知制限
- おやすみタイマー
iPhoneの制限方法
●スクリーンタイム
iPhone端末のスクリーンタイム機能を使う事でアプリやサイトの利用時間を確認する事ができます。
その他にも、アプリごとの利用時間制限や休止時間の設定などもする事ができます。
行える内容は以下になります。
- 使用状況の確認
- 時間制限
- 休止時間の設定
- ペアレンタルコントロール
●ファミリー共有
iPhoneのファミリー共有のペアレンタルコントロール機能を使えば、子供の端末利用を制限できます。
具体的にはアプリ制限、コンテンツ制限、購入の承認の有無などを設定できます。
行える内容は以下となります。
- ペアレンタルコントロール
- コンテンツ購入の承認の有無
- アプリ制限
- コンテンツ制限
- 位置情報の共有
「ファミリーリンク」や「ファミリー共有」を用いての端末の利用制限の方法については、以下の記事でも詳しく解説しております。
▼

「スマホは小学生にとって悪影響なのか?」のまとめ
小学生がスマホを持つ事によって、
- 視力への影響
- 睡眠への影響
- 勉学への影響
- 運動への影響
など様々な悪影響を及ぼす可能性があるという事が分かりました。
小学生がスマホを持つ事によって、悪影響を受けないようにするためには「利用時間」「利用場所」「アプリ」「課金」「個人情報」などに気を付ける事で防ぐ事ができます。
具体的な方法については、
- 親が子供のスマートフォンの利用状況や時間を管理する
- キャリアから提供されているフィルタリングサービスを利用する
- 端末に搭載されている利用の制限機能を使う
などがございます。
その中でも、キャリアから提供されているフィルタリングサービスは簡単に設定を自由自在にカスタマイズする事ができるのでオススメです。
フィルタリングサービスを提供しているキャリアは「楽天モバイル」「LINEMO」「Y!mobile」「mineo」「ahamo」などがございます。
皆さんもこの機会に、事前にしっかりと準備を行ったうえで小学生のお子様にスマホを持たせてみてはいかがでしょうか?