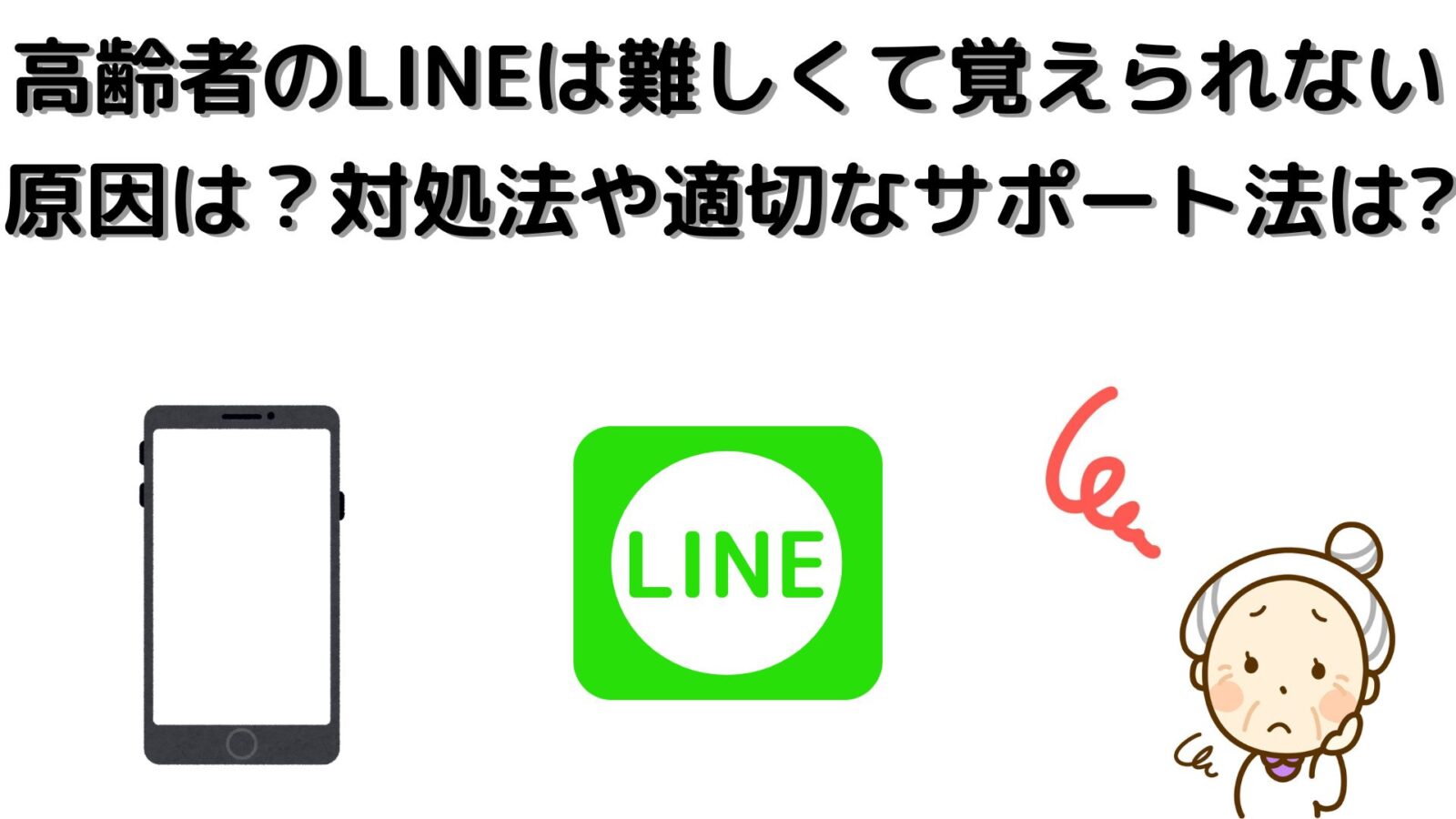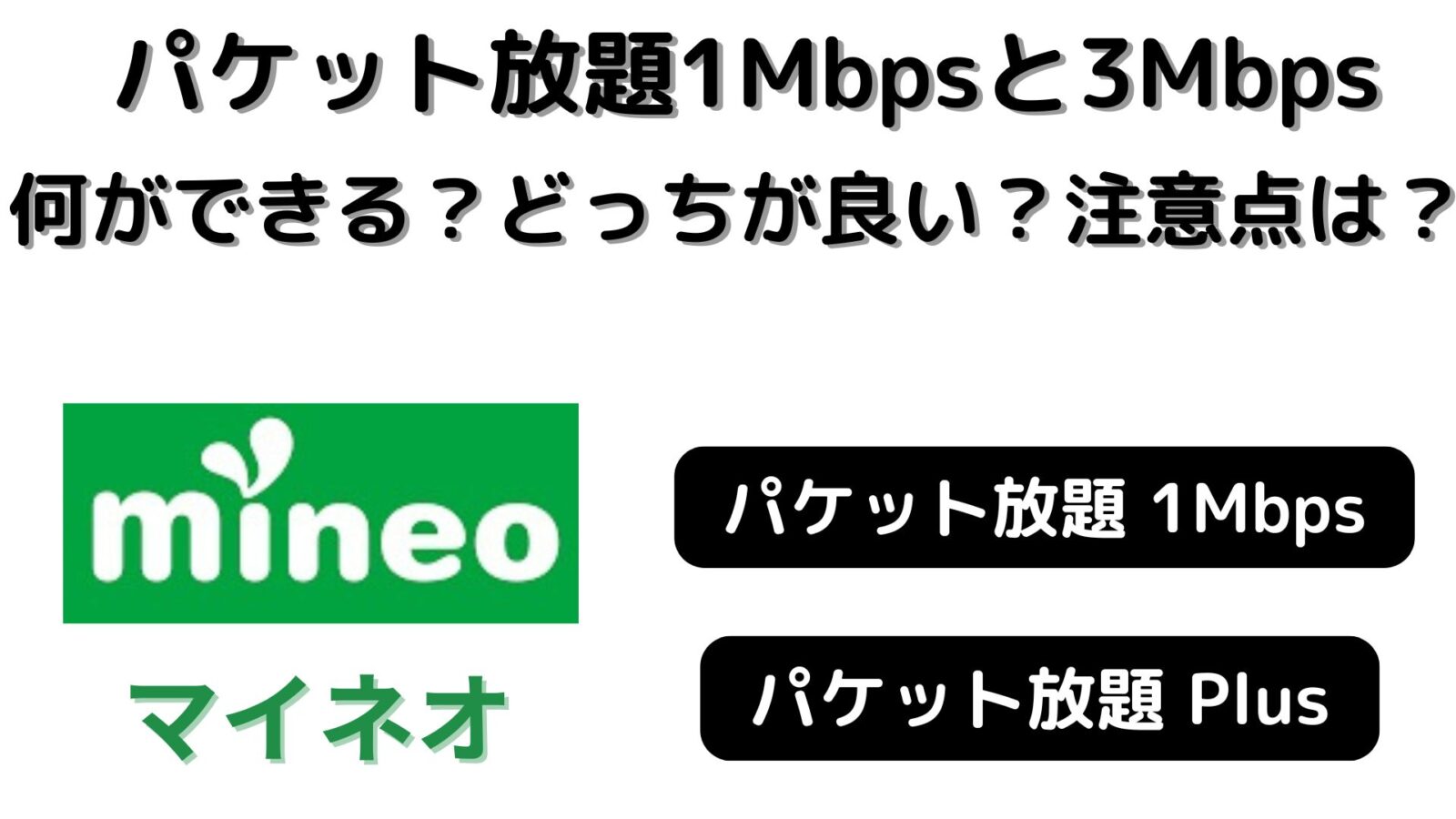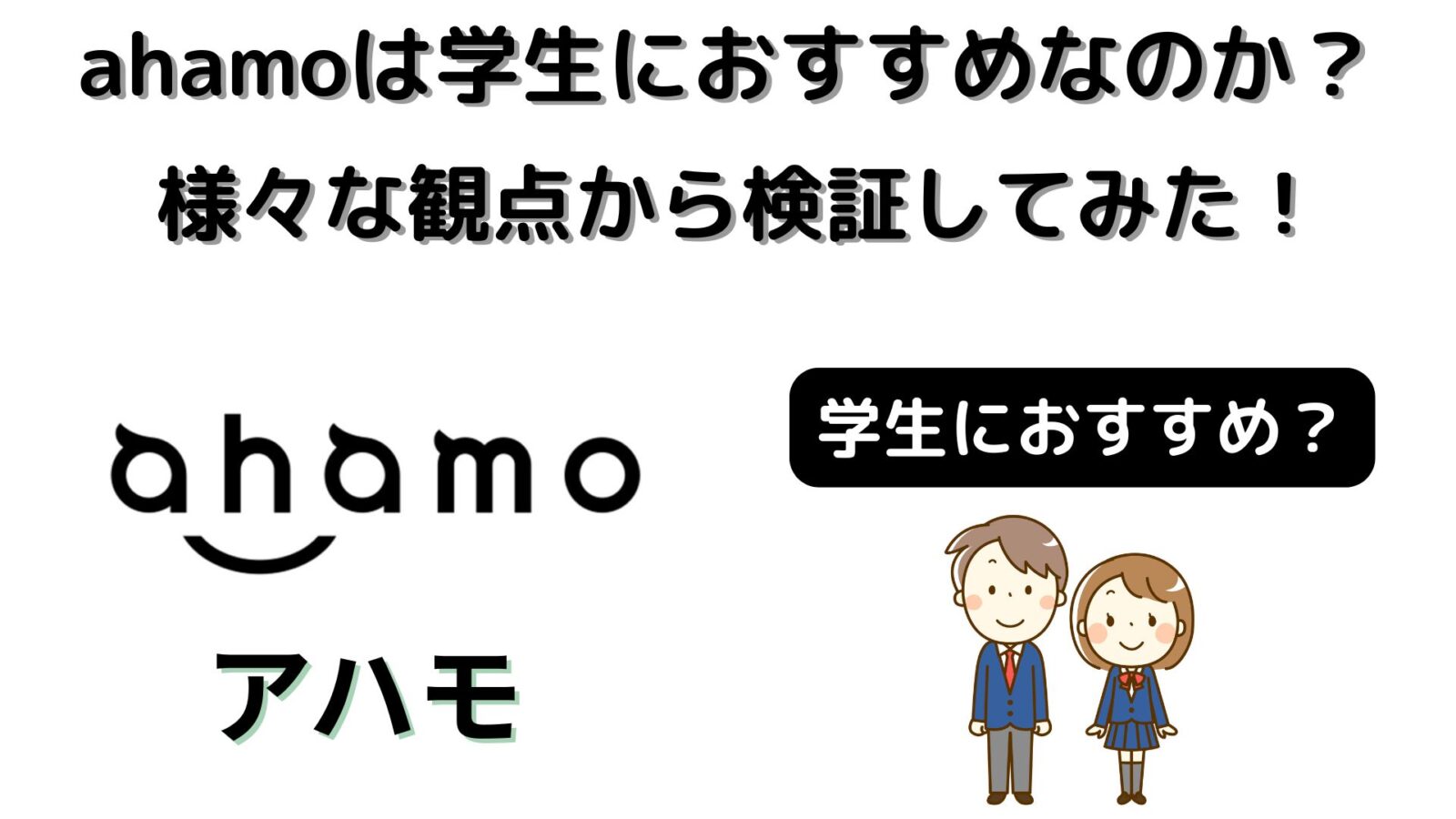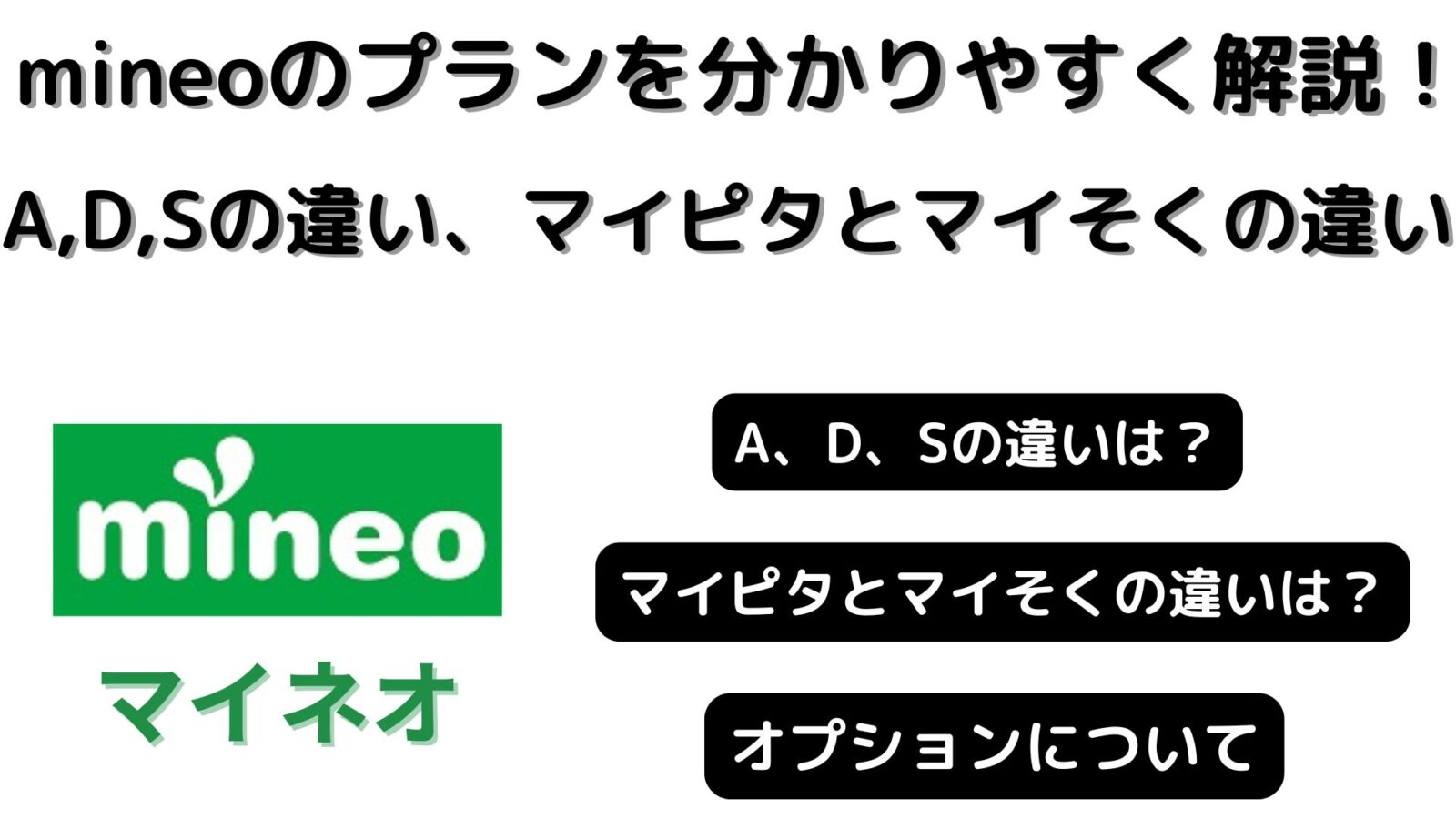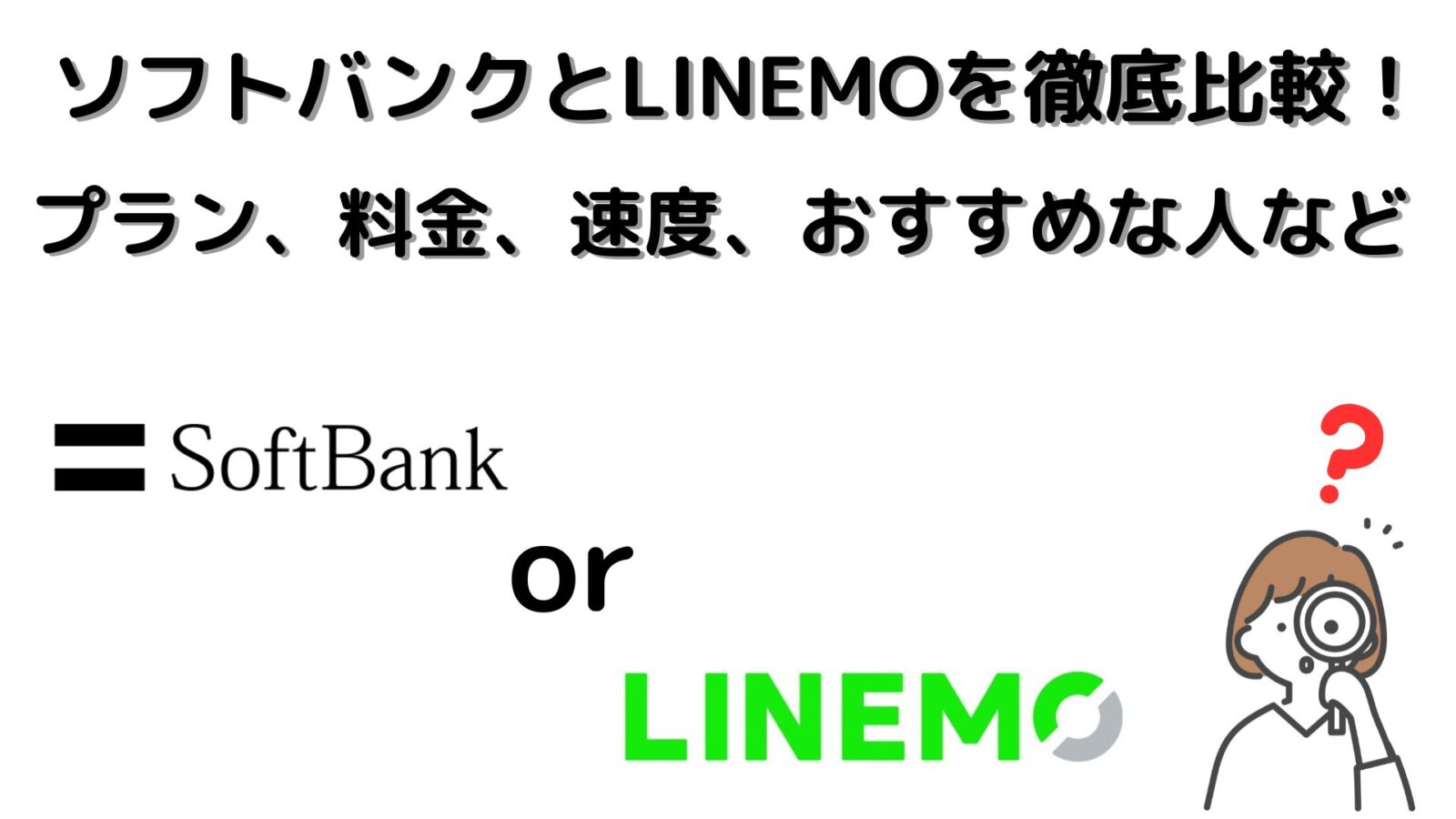高齢者のLINE利用が難しくて覚えられない原因
高齢者がLINEを利用するのが難しいと感じる理由としては「スマホのタッチパネル操作に慣れていない」「設定が負担となっている」「通知の音量などを調整できない」「チャットのスピードに対応できない」「新機能を理解するのが難しい」などが挙げられます。
これらのハードルを少なくするためには、家族が一緒に寄り添って教えたり、文字サイズを大きくして入力しやすくしたり、マナーモードの設定の仕方を教えたり、設定を代わりに行ってあげたり、使い方をマスターするまで根気強く付き合う、などといった物理的、心理的の両面でのサポートが必要になります。
この章では高齢者のLINE利用が難しくなる原因について、一つ一つ紹介させて頂きます。
スマホ操作自体が難しい
高齢者のスマホ操作は「視力の衰え」「指先の器用さの低下」「指先の乾燥のしやすさ」など年齢によって生じるものと、「新しい事への抵抗感」「技術の習得自体が苦手」「アプリや端末の不調」など多様なものがネックとなり、難しいと感じやすくなります。
これらは加齢による身体的変化、長時間使用によって起こる身体的な負担、一人で悪戦苦闘する事による精神的負担、そして操作の技術的な問題など、様々な要因が絡み合って起こります。
身体的な要因
- 加齢によるもの
高齢になればなるほど、指先の乾燥、筋力の衰えなどによってタッチパネルが反応しづらくなったり、視力が衰える事により小さな文字が見えにくくなります。
- 首への負担
スマホを操作する際に前かがみの姿勢になりやすく、それが首や肩への負担を増大させ、肩が凝ったり、首の痛みへと発展する場合があります。
- 手への負担
スマホは片手で操作するケースが多く、それが手首への負担となり腱鞘炎を発症したり、何度もタッチする操作を繰り返す事で指先を痛めたりする場合があります。
- 目への負担
スマホを長時間利用し続けると、自然とまばたきをする回数が減ってしまい、ドライアイを引き起こしやすくなります。
また、画面を凝視し続ける事によって眼精疲労にもなりやすいです。
精神的な負担
- ストレス
長時間のスマホの使用は、睡眠不足を招いたり、集中力が低下しやすくなったり、依存しやすくなったり、うつ病などのリスクを高める要因となる場合がございます。
- 認知機能
スマホに頼り過ぎる生活をしていると、認知機能が落ちたり、記憶力が衰えたり、言語能力が低下するなどして、それがスマホ操作の難しさにつながる事があります。
技術的な要因
- 端末の不調
ストレージの容量が不足していたり、キャッシュが溜まっていたり、保護フィルムが適正に貼れていなかったりすると、端末の動作が低下したり、タッチパネルの精度を低下させる要因となります。
- 設定の困難さ
文字入力のパターンや画面の明るさ、文字の大きさなど設定が適切に行われていないと操作を困難に感じやすくなります。
LINEの新規登録で躓く
新規登録
LINEの新規登録が難しいと感じる要因としては「LINEアプリをインストールする作業で躓いてしまう」「SMSが受信できる電話番号が必要である事」「入力内容を間違えやすい」などが挙げられます。
とくに、SMSを受信できないWi-Fiモデルのタブレットでは登録自体ができないため、代わりの端末を用意したり、固定電話などから登録をする必要がございます。
電話番号認証ができない
- 新規登録する際に、SMSが受信できる電話番号が必要になります
- Wi-Fiモデルのタブレットなど、SMS機能がない端末では登録ができません
- 050で始まるIP電話の番号では登録する事はできないため、090/080/070などから始まる電話番号が必要となります
入力間違え
- LINEに登録する電話番号に認証番号が送られてくるため、電話番号は正確に入力する必要があります
- 送られてくる認証番号は6桁と多いため、番号を間違えて入力しやすいです
- 認証作業を何度も失敗すると、制限される事があるため、落ち着いてゆっくりと作業する事が求められます。
設定の困難さ
高齢者でLINEの設定が難しいと感じるのは、セキュリティの設定やプライバシーに関する設定項目などが多岐に渡るためです。
とくに、他者からの不正ログインを防ぐ「ログイン許可のオン・オフ」、IDにて友だち追加できるようになる「IDによる友だち追加のオン・オフ」そして、友達が自動で追加される「友だち自動追加のオン・オフ」は初心者には理解しづらく、高齢者にとってはより苦労しやすいでしょう。
LINEアプリの主な設定
- ログイン許可
ログイン許可をオフにする事で、見知らぬ端末からのログインを防ぐ事が可能です。
- IDによる友だち追加
この設定をオフにする事で、自分のLINE IDを知っている相手が友だち追加をリクエストする事ができなくなります。
- 友だち自動追加
この設定をオフにすると、自分の電話番号を電話帳に登録している人が自動的にLINEの友だちに追加される事を防ぐ事ができます。
- パスコードロック
第三者がスマホ端末を開いてもLINEを見れないように、LINEアプリを開く際にロックを設定する事ができます。
- 情報提供
こちらをオフにする事で、自分の利用した情報を提供しないようにする事ができます。
通知の設定が難しい
スマートフォンの通知はアプリが新しい情報や更新、メッセージなどがあった場合にスマホの画面に表示をして、知らせてくれる機能になります。
スマホを使用中は画面の上部、ロック画面時には中央部に表示され、利用者は通知をタップする事で簡単にLINEアプリを起動して、内容を確認したり、返信をしたりする事が可能です。
LINEアプリの通知以外では、メール、SNS、ニュース、OSの更新、カレンダーの予定などが通知され、リアルタイムにてスムーズに確認しやすくなっています。
しかし、高齢者は通知設定が難しいと感じる場合が多く、公共の場などでスマホが鳴り響いてしまったり、マナーモードに設定できなかったりする事で、LINEアプリの利用を避けてしまう原因になる場合がございます。
通知の音量設定(マナーモード)ができない事による影響
- 周囲への影響
公共の場所など静かな場所にて、着信音や通知音が鳴り響いてしまうと、周囲の人々が不快に感じやすくなります。
- 作業への影響
家事中や食事中など、何か作業に集中したいという時に通知音や着信音が鳴ってしまう事で集中力が途切れやすくなってしまいます。
- 睡眠への影響
就寝前などリラックスをしたい時間帯にて、大音量にて音が鳴ってしまうと興奮状態となり、入眠への準備が妨げられやすくなります。
- 精神への影響
通知音で頻繁にお知らせが届くことによって、時間に追われている感覚となり、心が落ち着かない状態で生活する事となります。
機能を理解していない
LINEのアプリは「メッセージの送受信」「音声通話での会話」「ビデオ通話での会話」「写真の送信」「動画の送信」「現在地の共有」「アルバムを使っての共有」など、多種多様なコニュニケーション機能を提供しています。
また、この他にも送られてきたメッセージの内容を忘れないようにするためにピン留めをする「アナウンス機能」や一度送った送信が間違っていた時に取り消しができる「送信取り消し機能」などの便利な機能も提供されています。
しかし、これらの多くの便利機能が却って、高齢者が覚えるのに負担になってしまっているケースもございます。
重要なのはどのような機能を使いたいか、または必要になるかを見極めながら、覚えるものを取捨選択する事が重要となります。
LINEの主な機能一覧
- トーク機能
テキストメッセージ、スタンプ、写真、動画、現在地情報、音楽など多種多様なメディアを共有する事ができます。
- 通話機能
音声通話、ビデオ通話などで実際に会話をしながらコミュニケーションを図る事ができます。
- 送信取り消し機能
1度送ったメッセージに間違えなどがあった場合に、後から送信を取り消す機能となります。
- アナウンス機能
忘れずに覚えておきたいメッセージの内容を「アナウンス」として、上部にピン留めする事が可能です。
- 現在地の共有
メッセージをしている相手に、今いる場所を地図上にて共有する事ができます。
やり取りのスピードについていけない
LINEのやり取りのスピードについていけないという状況は「アプリの動作が遅くなってしまっている状態」と「相手の返信するスピードについていけない状態」の2パターンが考えられます。
動作が遅くなっている場合は、アプリのキャッシュを削除したり、再起動をする事で比較的簡単に解決する事ができますが、相手の返信するスピードになかなかついていけない場合には長期間の練習が必要となります。
多くの場合、後者である可能性が高く、そのようなケースでは返信を焦らなくて良いと事前に伝えたり、時間に余裕をもってメッセージを送っておいたり、返信の締め切りを長めにしておくなどといった工夫が求められます。
相手の返信スピードについていけないケース
- 返信頻度が合わない
相手の返信する頻度がご高齢の方とあっていない場合、イライラする事があります。
マイペースな性格など相手の性格を考慮した返信頻度にする事が求められます。
- スピードが速すぎる
どんどん一方的にメッセージを送ってしまうと、相手を焦らせる要因となります。
早く送り返さないといけないという印象を与えてしまいかねないので注意が必要です。
- 時間や締め切りに余裕が無い
早く返信が欲しい時や、返信の締め切りが迫ってきてからLINEのメッセージを送ってしまうと、相手にとってはじっくりと考える余裕が確保できずに、負担となってしまう場合があります。
- アプリが重くなっている
LINEのアプリ内に一時的に保存されたキャッシュデータなどが溜まっている事で動作が遅くなり、スムーズに文字入力ができなかったり、読み込みができなくなる場合があります。
高齢者のLINE利用が難しくて覚えられない場合の対処法、解決策
高齢者のLINE利用が難しくてなかなか覚える事ができない場合には「音声入力を活用する」「よく連絡を取る相手をピン留めする」「端末のかんたんモードやシンプルモードを活用する」、そして「家族が親身に寄り添ってサポートする」などが有効となります。
また、どうしてもLINEをマスターする事が難しい場合には、LINE以外の連絡手段も検討する事が求められます。
現在は、高齢者が使いやすいように配慮されているシニア向けスマホや電話とメールを使う事に特化したガラケースマホ(ガラホ)なども発売されておりますので、そういった端末を活用するのも良いでしょう。
この章では対処法や解決策についてご紹介しますので、ご高齢の方と連絡できる手段が欲しいという方はぜひ参考にして下さい。
音声入力機能を活用する
LINEでの文字入力に苦労している場合には、スマートフォンに標準搭載されている音声入力機能を活用する事が有効となります。
具体的な手順としては、LINEアプリでのトーク画面にてマイクアイコンをタップして音声入力を開始する事ができます。
注意点としては、正確な入力をするにははっきりとした発音で喋る事が必要な事と、入力したい内容に個人情報が含まれる場合には第三者に聞こえないように注意するといった事が求められます。
音声入力の詳細
- 声が文字に変換
LINEアプリにてメッセージ入力欄の右下にあるマイクのマークをタップして、スマホのマイクに話す事で声が文字に変換されて入力できます。
- 記号や句読点の入力
「ぎもんふ」と入力すると「?」と出力されたり、「てん」と入力すると「、」と出力されたり、「まる」と入力すると「。」と入力されるなど記号や句読点も入力できます。
- 負担の軽減
スマホを利用する際に高齢の方はキーボード入力が身体的な負担となるケースが多いです。
音声入力にすると端末を置いたままでも入力する事ができるので、手や手首に負担を掛けずに文字を入力する事ができます。
ピン留め機能を使う
LINEアプリでのトーク画面にてピン留め機能を使うと、その人のトークルームがチャット一覧の上部に固定され、アクセスがしやすくなります。
そのため、よく連絡を取り合う人のトークルームをピン留めで固定しておく事で、操作を簡略化する事ができます。
LINEアプリでピン留めをするには、Androidではトークルームを長押しする事で可能です。
iPhoneの場合はトークルームを右にスワイプして表示されるピンのマークをタップする事で可能となります。
解除する際もAndroidの場合は長押し、iPhoneの場合はスワイプで解除する事ができます。
トークルームのピン留め方法
Androidの場合
- ピン留めしたいトークルームを長押しします
- メニューが表示されるので「ピン留め」をタップ
- チャット一覧の上部に、選択したトークルームが固定表示されます
iPhoneの場合
- ピン留めしたいトークルームを、右にスワイプします
- メニューが表示されるので「ピンのマーク」をタップ
- チャット一覧の上部に、選択したトークルームが固定表示されます
返事のしやすい質問にする
やり取りするメッセージはできるだけ「はい」か「いいえ」で答えられるようにするなど、質問を返事のしやすいように工夫すると良いでしょう。
また、いくつか選択肢を明示して、その中から返事をしてもらうといった事も相手が返事を考える手間が省けるので返答しやすくなります。
その他にも、スタンプで答えたり、選択肢を番号で答えてもらうといった事も有効です。
ポイント
- 「はい」「いいえ」で回答できる
なるべく、質問する形は「はい」と「いいえ」の二択で答えられるように工夫すると相手は簡単に返事をする事ができます。(クローズドクエスチョン」
- 回答の選択肢を明示する
いくつか回答の選択肢を掲示して、その中から回答を選んでもらうとスムーズに返信しやすくなります。
- 番号で答えてもらう
回答の選択肢に番号を振っておくと、相手は番号で答えるだけで良いのですぐに回答を返す事ができます。
家族がサポート
高齢者がLINEの利用が難しくて覚えられない場合には、スマホ操作に慣れているご親族の方がサポートしてあげるのも有効な手段となるでしょう。
ご親族やご家族の方がご高齢の方のスマホの操作をサポートする時は「根気強く教える」「簡単な事から徐々にステップアップしていく」「遠隔サポートをしてあげる」などが大切となってきます。
また、キャリアのチャットサポートを利用したり、スクショを送ってもらったり、通話をしながら操作方法を説明してあげるのも良いでしょう。
離れていても分からない事があれば、いつでも聞いて良いという雰囲気を作って、安心させてあげる事が重要となります。
サポートのポイント!
- 粘り強く教える
失敗したり、正しくできなくても、否定的な発言はせず、何度も優しく丁寧に教えてあげる事が大切です。
使い方をマスターした際には、一緒に喜んであげる事でモチベーションの維持にも繋がります。
- 一緒に操作
教える方が実際にスマートフォンを操作して、具体的な操作方法を見せてあげるのも早くマスターできる秘訣となります。
対面で教える事が可能な場合は、実際に直接会って教えてあげるようにしましょう。
- 簡単な事から少しづつ
いきなり難しい事にチャレンジするのではなく、まずは電源を入れたり、アプリを起動したり、電話を掛けたり、何かしらの文字を入力したりといった初歩の基本的な操作から始め、成功体験を積み重ねる事で途中で挫折しにくくなります。
- 何度も聞ける雰囲気作り
分からない事があったら、いつでも気軽に聞いても良いという雰囲気をご家族やご親族の方が作り出してあげる事で、「間違えたらいけない」「忘れてはいけない」という不安感を無くすことができ、安心してスマホの操作に専念する事ができます。
かんたんモード
シニア向けスマホには文字やアイコンを大きく見やすく表示できるようにしたり、操作をシンプルで使いやすくできる「かんたんモード」や「らくらくモード」という機能が搭載されています。
その他にもホーム画面をカスタマイズしてアイコンを大きく表示したり、誤タッチを防ぐための配慮などもされています。
シニア向けスマホの特徴
- 文字やアイコンが大きい
見やすくなるような工夫が沢山施されており、文字が読みやすくなったり、アイコンが探しやすくなっています。
- シンプルな操作
ホーム画面のアプリが必要なものしか配置されていなかったり、画面がごちゃごちゃとしていないなど、高齢の方でも迷わずに操作できるようになっています。
- カスタマイズできる
よく使う連絡先を押しやすいように大きく表示したり、よく使うアプリが大きく表示されていたりと、ワンタッチで通話やメッセージなどが送れるようになっています。
- 誤操作しにくい
強く押す事で認識されるようになっていたり、長押しする時間が長くなっていたりと誤操作を防ぐ配慮が多く備わっています。
- 豊富なユーザー補助
拡大鏡が使えるようになっていたり、キーボードを見やすい配色にできるなど、視力の低い方であっても難なく操作ができるような補助機能が付いています。
シニア向けスマホならY!mobile!
シニア向けスマホである「らくらくスマートフォン」「かんたんスマホ」が好評販売中!
\ワイモバイル公式HPで詳細をチェック/
シニア向けスマホならSoftBank!
シニア向けスマホである「シンプルスマホ」が好評販売中!
\ソフトバンク公式HPで詳細をチェック/
その他の連絡手段を検討
何回練習をしてもLINEを利用するのがなかなか難しい、使いこなす事ができないというご高齢の方は連絡手段をLINE以外にするというのも一つの方法です。
そこでオススメなのがスマホからガラケー(ガラホ)に乗り換えて、連絡手段を電話やメールに切り替えるという方法です。
高齢者がガラケー(ガラホ)を使うメリットとしては「物理ボタンで操作できる」「本体が壊れにくい」「通信費が安い」「バッテリー持ちが良い」「シンプルで簡単な操作性」「詐欺被害のリスクが低い」などが挙げられます。
スマートフォンの複雑な操作に慣れない方や必要最低限の連絡手段だけあれば良いという方にとって、最適な端末となっております。
ガラケー(ガラホ)の利点
- 操作が簡単
タッチパネルではなく、物理的なボタンで操作する事ができるのでご高齢の方であっても、抵抗感が少なく操作できます。
- 月額費が安い
スマホと比べて利用できる機能が限られているので、月額料金を安く抑えられやすくなっています。
- 電池の持ちが良い
余計な機能が搭載されていないと、それだけ消費電力も少なく、スマホに比べて電池が長時間持ちます。
- 詐欺被害のリスク回避
利用できるサービスを必要最小限にする事で、ネット起因による詐欺被害に遭うリスクを低くする事ができます。
ガラケー型ケータイならY!mobile!
ガラケー型ケータイである「DIGNO ケータイ」「AQUOS ケータイ」が好評販売中!
\ワイモバイル公式HPで詳細をチェック/
ガラケー型ケータイならSoftBank!
ガラケー型ケータイである「かんたん携帯」「AQUOS ケータイ」「DIGNO ケータイ」が好評販売中!
\ソフトバンク公式HPで詳細をチェック/
まとめ「どうしてもLINEが難しいという場合はシニア向けスマホやガラケーへの乗り換えのご検討を!」
高齢者のLINE利用が難しくて覚えられない原因としては、
- 視力の衰えや指先の乾燥などの年齢的な不調と、新しい事への抵抗感や覚える事自体が苦手など、様々な要因によってスマホ操作が難しいと感じやすい
- LINEアプリをインストールする時点で躓いたり、SMSを受信して認証番号を間違えずに入力する必要があるなど新規登録をスムーズに行えない
- セキュリティを強化するための設定やプライバシーに関する設定など、設定する項目が多く用意されていて理解するのが難しい
- スマホの通知設定は新しい情報や更新があった際に知らせてくれる機能となりますが、ご高齢の方は通知の音量設定がうまく行えず、煩わしく感じやすい
- LINEアプリにはメッセージの送受信以外にも音声通話、ビデオ通話、動画像の送信、位置情報の共有など多くの機能が備わっており、理解するのに苦労する
- スマホのメンテナンスがうまく行えずアプリが重くなってしまっていたり、相手のメッセージの返信するスピードについていけないなどして挫折しやすい
などが要因として挙げられます。
高齢者のLINE利用が難しくて覚えられない場合の対処法としては、
- LINEでの文字入力が難しいという方はキーボード入力ではなく、音声入力を活用する事で声で文字を出力する事ができる
- トーク画面へのアクセスに戸惑ってしまうという方は、よく連絡を取り合う相手のトークルームをピン留めする事で上部に固定表示する事ができる
- ご高齢の方とLINEを用いてやり取りを行う場合には、なるべく短文で返事ができるように質問の仕方を工夫する事で相手の負担を軽減できる
- ご高齢の方がLINE利用に手こずっている場合には、親族やご家族の方がバックアップをしてあげる事で、より安心してLINEを覚える事に集中できる
- 高齢の方がスマホを利用するのに特化したシニア向けのスマホに乗り換える事で、画面が見やすくなったり、文字を入力しやすくする事ができる。
- どうしてもLINEを利用するのが難しいという場合には、ガラケー(ガラホ)に乗り換えて、LINE以外で連絡を取り合うようにする
以上のような解決方法がございます。
皆さんもこの機会にぜひ、ご高齢の方と連絡を取りやすい環境をつくってみてはいかがでしょうか?